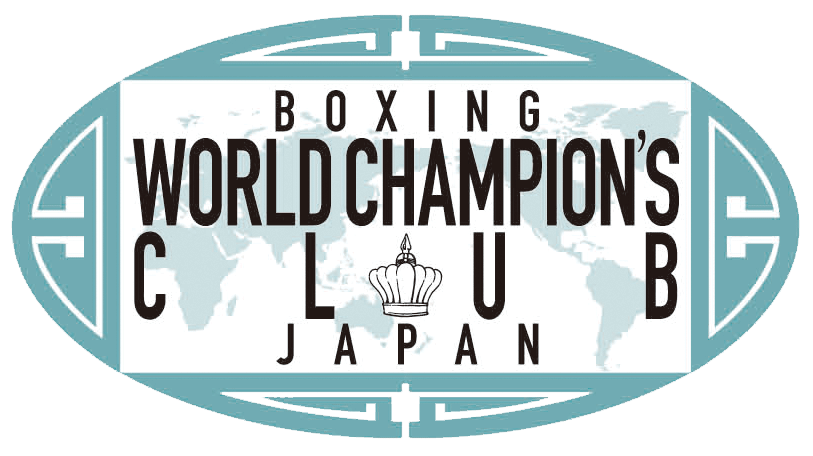浜田剛史さんは、1986年にWBC世界S・ライト級タイトルを獲得し、15連続KO勝の日本記録保持者でもあります。また現在、日本を代表する名門ジムの帝拳ジムの代表であり、昨年からは日本人の世界王者の会であるボクシング世界チャンピオン会の会長も務めています。現役引退後は、日本テレビやWOWOWで世界のビッグマッチの解説を35年以上担当してきました。内外のボクシング事情に精通しているだけでなく、ボクサーやトレーナーの立場に加えジムの経営や統括団体についても専門的な知識を持っておられます。この浜田さんを会長に、ボクシングの専門的な情報の意見交換をしてより広く深い視点からボクシングを考察していけるような組織である「ボクシング情報ラボ」(Boxing-Labo)が設立されました。今回は浜田さんが会長を務める世界チャンピオン会や昨今のボクシング事情についてお聞きし、さらにはこの「ボクシング情報ラボ」にはどのようなことを期待しているのか話していただきました。
世界チャンピオン会の活動について
浜田 : 日本のプロボクシングで、最初に世界チャンピオンになったのが1952年の白井義男さんでした。それから70年以上の間に100名を超す世界チャンピオンが出ました。2010年に日本人で世界タイトルを獲得した人の栄誉を称え、社会活動に繋げていこうというのが世界チャンピオン会が出来た理由です。ガッツ石松さんがしばらく会長をしていましたが、昨年から私が会長を務めることになりました。これまで東日本大震災や熊本地震や能登半島地震のためのチャリティ活動などをしてきましたが、これからもう少し情報発信するためにホームページを立ち上げたところです。白井義男さんが初めて世界タイトルを獲ったのが1952年5月19日だったので、毎年この5月19日を「ボクシングの日」として活動をしています。今年はこの日に水道橋の東京ドームホテルに、世界チャンピオン経験者が約40名集まってパーティーを行うことになっています。これまでこの世界チャンピオン会は基本的にはボランティアで運営されていたので、あまり大きな活動が出来なかったのですが、これから広報活動なども含めて、さらに充実したものにしていきたいと考えています。
近年の日本ボクシング界について
浜田 : 現在、日本のボクシング界は現役の世界チャンピオンが7人もいてまさに黄金時代にあると言えます。世界S・バンタム級の4団体を制覇している井上尚弥を筆頭に、バンタム級では4団体の全てで日本人が世界チャンピオンになっています。これはボクシング関係者やこれを支えてくれるファンの力があってできることですが、これから日本人ボクサーももっと世界の舞台で戦っていってほしいと思っています。ただどうしてもボクシングはプロの世界タイトルマッチばかり注目されますが、若いボクサーの育成やジムの経営などは簡単ではありません。これまで日本のボクシング界では、日本ボクシングコミッション(JBC)とジム経営者の団体である日本プロボクシング協会(JPBA)があって、ライセンス、ルール、等を取り扱ってきました。またプロとアマチュアではそれぞれの団体の方針で運営をしてきたため、日本のボクシング全体の発展に協力する体制になってきませんでした。最近ではボクシングのジムには、女性や子供たちもフィットネスやボクササイズのために来る人たちも増えてきているそうです。世界チャンピオン会としては、このような別々の世界の橋渡しをして、ボクシング全体の普及と発展に尽力していきたいと考えています。
プロボクシングでは4団体17階級にタイトルが増えたことについて
浜田 : 今、日本で公認されている世界タイトルの団体は、WBA、WBC、IBF、WBOの4団体あります。日本では、長年JBCはWBAとWBCの2団体しか認めてこなかったのですが、その後、世界のボクシング界が大きく変化してIBFやWBOの世界チャンピオンの中には、WBAやWBCのチャンピオンよりも実力が上だと見られる選手も出てきました。4団体が承認されるまで賛否両論ありましたが、様々な議論を経たのちに2013年にJBCも正式にIBFとWBOも認めて、日本人ボクサーがIBFやWBOの世界タイトルに挑戦できるようになりました。これによって特に軽量級では4団体で日本人の世界チャンピオンが誕生することが可能になったわけです。同じ階級の世界タイトルが増えることについては、反対意見も多くありました。そして正規王者のほかに、暫定タイトルやスーパータイトルや、休養チャンピオンなど、意味不明のタイトルも出てきたりして、そういう傾向に批判があったことも事実です。暫定王座については、元々は正規王者が不慮のケガや事故などのために試合が出来なかった場合、特別措置として暫定的に世界タイトルを認めるということから最初はWBAが採用したものでした。ところが、ひとつのタイトルでも正規タイトルと暫定タイトルで両方試合を行えばライセンス料が両方から取れるので、この暫定タイトルが必要以上に乱造されてきたことは否定できません。これがWBCやIBFにも拡大してしまい、世界チャンピオンの価値が相対的に下がってしまうのではないかという懸念も出てきました。そのため近年では世界タイトルを持つことが目標ではなく、真の世界一を示すためには、世界タイトルの統一戦をしたり、複数階級制覇をしたりすることが増えてきました。ボクサーにとっては世界タイトルを獲るチャンスが広がったという面はありますが、さらに高い評価を得るためには、同一階級の統一戦や複数階級制覇をしなければならなくなったので、一層大変になった面はあります。それでも4団体が公認されたことで、日本人ボクサー同士がお互いに刺激し合って、どんどんレベルアップしていくのは、とてもいいことだと思いますよ。世界に通用するようなボクサーが、どんどん出てきてほしいものです。
ボクシングを巡るメディアの変化について
浜田 : ボクシングの世界タイトルマッチは、これまでずっとテレビで生中継されてきたのですが、ここ数年でネット配信に大きく変わってきました。それからボクシングの情報という点では、新聞社にはボクシング担当の記者の人がリングサイドに来て取材していましたし、ボクシング専門誌の記者やカメラマンの人たちも定期的に情報発信してくれていました。ただここ数年で、インターネットを経由してパソコンやスマホで情報を伝えることが多くなり、ボクシングを巡るメディア状況も大きく変化しています。これにはメリットとデメリットがあると思いますが、メリットとしてはネット配信になると、どこでも手軽にボクシングの試合を動画で見ることが出来るようになることです。テレビがなくても、移動中でも試合をライブで見ることができるようになるので、利用者の拡大という点ではいいことでしょう。その反面デメリットとしては、本来であれば料金を払って見るようなボクシングの貴重な映像でも、著作権などの権利関係が殆ど無視されるような形で無料でネット上に出回ってしまうことではないかと思います。そして従来までは過去の貴重な映像はテレビ局がきちんと記録管理していたものが、ネット配信になると記録管理をしっかり行っていくところがなくなってしまう心配も出てきます。
それから今、世界タイトルマッチなどの配信は、Amazon-PrimeやAbemaやU-NEXTなど、新興のネット配信サイトで行われるようになりましたが、この体制がこのまま続いていくのかどうかはよく分かりません。番組を中継したり編集したりするスタッフは、ある程度ボクシングのことを知っている必要があるのですが、そのようなスタッフの教育や育成が今後やれるのかどうかも不安なところです。今から35年も前になりますが、WOWOWでエキサイトマッチが始まったとき、初めての有料チャンネルで世界のボクシングの試合を定期的に放送することになりました。私もWOWOWが開局したときからずっとこの番組の解説をしてきましたが、35年という時間をかけて番組自体がスタッフも含めて育ってきたところがありました。これからボクシングの試合を伝えるメディアの中心がネット配信になったとしても、やはり時間をかけてスタッフの人たちが経験を積んでボクシングの専門的なことを勉強していけるような環境を作っていってほしいと思います。
ボクシング情報ラボについて
浜田 : ボクシング情報ラボは、3年ほど前からボクシングの情報を専門的に扱うシンクタンクのようなものがあればよいのではないかということで、話が上がっていました。日本で世界チャンピオンが誕生してからすでに70年以上、歴代の世界チャンピオンは100名を超えました。また世界のボクシングも、今ではWOWOWやネットを通してリアルタイムで見ることが出来るようになりました。このようなボクシングが歩んできた歴史を、より専門的な立場から研究したり分析したりすることも大切です。例えば、ボクシングはボクサーの健康管理が特に重要視されますが、その基準は日本と世界ではどのように違うのかを比較分析することも必要でしょう。ボクシングは世界中で行われる競技なので、異なる国の選手や異なる文化を持つ選手同士が対戦することも多いのですが、お互いに共通した基準や考え方を共有することは結構難しいことなのです。
それから現代のボクサーの活躍を知るだけでなく、何年か時が経ってから過去の試合の意味を、もう一度検証することも大切でしょう。ファイティング原田さんの時代、具志堅用高さんの時代、そして井上尚弥君の時代。それぞれ時代を代表するヒーローですが、どういう時代や社会だったのかを歴史的に考えてみる作業はあまり行われていません。社会や価値観の変化は、それぞれの時代のボクシングにどのように表れているのかを再評価することも必要です。
そしてボクシングは、同時代を生きている人間のドラマでもあります。世界の動向の中でボクシングがどのように関わってきたのかを考察することも、これからもっと必要になるも思います。
1990年代になって冷戦が終わると、旧ソ連のアマチュアの強い選手がプロ入りして世界タイトルを獲っていきました。日本のジム所属では、勇利アルバチャコフ(旧ソ連・ロシア)やオルズベック・ナザロフ(旧ソ連・キルギス)が世界チャンピオンになりました。彼らはあの時代を象徴するボクサーでした。
それと同じように、今ロシアと戦争をしているウクライナからは、ヘビー級ではビタリ・クリチコとウラディミール・クリチコのクリチコ兄弟が一時代を築きました。兄のビタリは、その後、政治家になって、今は首都キーウ市長として頑張っていますね。またウクライナと言えば、現在のヘビー級統一チャンピオンのウシクや、中量級のスーパースターのロマチェンコもいます。彼らがただ単にボクシングの試合をするというだけでなく、そのようなウクライナの歴史や政治と合わせて考えていくことも大切なのだろうと思います。
このようにボクシングを広い視点から見て、その背景や文化まで深く考えるような組織があるといいと思うのです。多くの場合、ボクシングは誰が勝った誰が負けたという現在の情報しか見えていませんが、専門的な知識や情報を持っている人たちが集まって、いろいろ情報交換を行いながら考察したり分析したりするような組織があるといいと思います。そういう点で、ボクシング情報ラボには、これからボクシングのシンクタンクのような役割を果たしてもらえるよう期待しています。

会長:浜田剛史
1960年生まれ。元・WBC世界スーパー・ライト級王者。1986年、レネ・アルレドンドを1RKOし世界タイトル獲得。現在、帝拳ジム代表、世界チャンピオン会会長。
日本テレビ、WOWOW等で35年以上、解説者を務める。15連続KO勝利の日本記録保持者。