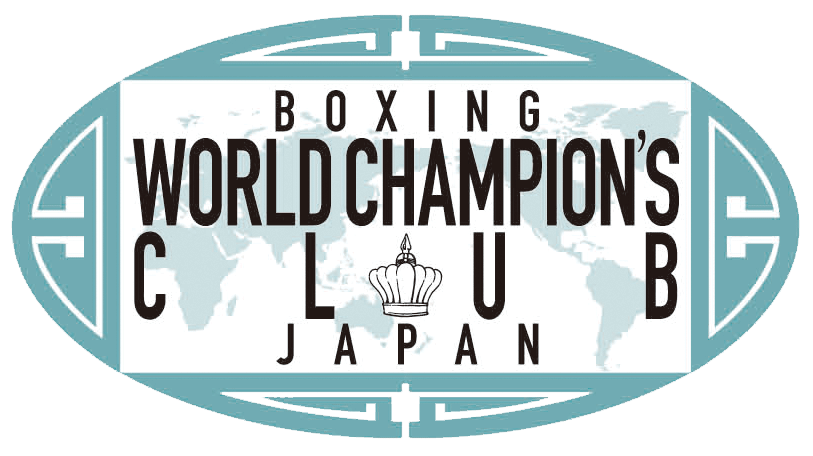今回は、ボクシング情報ラボ(Boxing-Labo)の今村庸一 理事長から、ボクシングとの関わり、放送作家時代の仕事、そして大学教授としての研究等について触れ、「ボクシング情報ラボ」への抱負なども語ってもらいました。
ボクシングとの関わりについて
今村 : 私自身はボクシングの経験があるわけではありませんが、子供の頃からボクシングはテレビでよく見ていました。一番最初に見た世界タイトルマッチで覚えているのは、私が小学校1年生のとき、1962年にファイティング原田さんがポーン・キングピッチをKOして世界チャンピオンになった試合でした。キングピッチをコーナーに詰めて原田さんの雨霰(あめあられ)のような連打を浴びせたシーンが強く印象に残っています。まだ私は小学1年生でしたからボクシングや世界タイトルについてもよく分かっていなかったと思うのですが、当時のフジテレビで生中継されていたボクシングの試合は空前の高視聴率を記録し、大人も含めて日本中熱狂の渦になっていたのがとても興味深く思いました。そこには非日常的な空間があって、多くの人を引き付ける何かがボクシングとテレビにあるのではないかと、子供心に感じたのだと思います。その後、私は紆余曲折を経てプロの放送作家になり、またテレビをはじめメディアやジャーナリズムを専門とする大学教授になったわけですから、この試合が私の人生の方向を決めた要因のひとつになったのかもしれません。それからはボクシングの世界タイトルマッチは、ほとんど見逃さずに見るようにしました。
中学生になると、私は毎月のように本屋でボクシング雑誌を立ち読みしていました。1970年代に入った頃、ボクシングの専門誌は「プロレス&ボクシング」と「ゴング」の2誌がありましたが、当時は両方ともプロレスとボクシングが同じ格闘技のジャンルとして月刊誌で扱われていたのです。中学生には少し値段が高かったので、この2誌は本屋で立ち読みをしながら、記事の内容と掲載されている写真の殆どは暗記するようにしました。このときの記憶が、後にWOWOWでエキサイトマッチの構成を担当したときに結構役に立ちましたよ。まもなくしてプロレスとボクシングは別物だということになってボクシング誌として独立し、それぞれ「ボクシングマガジン」と「ワールドボクシング」としてボクシングの専門誌になりました。
当時はインターネットもない時代でしたから、海外のボクシングの情報はこの専門誌に掲載されているものが全てでした。そのため世界的に有名なボクサーでも、写真で顔は知っていても実際の動画はなかなか見る機会がありませんでした。スポーツ情報は映像が大切です。私自身は研究者として映像メディアの歴史も専門に扱ってきましたが、ボクシングを伝えるメディアこそこの半世紀の間に本当に大きく進歩したと思います。ファイティング原田さんの時代は地上波の白黒テレビで一般家庭では録画は出来ませんでした。それが1970年代にはカラーテレビが普及し、1980年代になるとVHSやβなどの家庭用ビデオデッキが開発されました。ボクシングの視聴者にとっても、この変化はとても大きなものだったはずです。そして1990年代にはパソコンやインターネットが世界的に広がり、2000年代にはスマホ等のモバイル端末や動画配信アプリなども開発されていきました。この間、ボクシングのビッグマッチとメディアの開発普及というのも、まさに並行していったわけです。そういう点でも、ボクシングはメディアの研究対象としてもとても興味深い分野です。
放送作家時代の仕事について
今村 : テレビの仕事を始めたのが1982年からでした。当初はいろいろなことをしましたが、スポーツのドキュメンタリー番組を半年間、担当することがあって、そのときにテレビ番組の企画・制作の知識を得ました。1984年から約10年間、オフィス・トゥー・ワンという事務所に作家として専属契約をすることになりました。久米宏さんや安藤優子さんなどが所属していた事務所です。私自身はメディアやジャーナリズムの研究も並行していこうと考えていて、実は前年に某出版社のノンフィクション賞の最終選考に残って候補作になったので、出来ればノンフィクション系の作家かジャーナリストになることを考えていました。しかしオフィス・トゥー・ワンでは1986年からテレビ朝日の「ニュースステーション」を制作することもあり、久米さんを中心に報道番組のキャスターや作家を充実させたいという意向があったので、私には報道情報系やスポーツ系の放送作家の仕事が期待されました。テレビやラジオの番組のほか、イベントや雑誌の企画も数多く担当することになりました。
私は元々は法学部出身で国際法や国際政治が専門だったのですが、それまでの放送作家というとエンタメ系やワイドショーの作家はいましたが、政治や法律や国際問題を専門的に扱える人材はあまりいなかったので、その方面の番組を担当することが期待されていたのだと思います。1980年代の後半から1990年代の前半にかけて民放各局では報道番組の枠が大幅に拡大して報道戦争などど呼ばれたりしました。当時一緒に仕事をしたキャスターを挙げると錚々たるメンバーがいます。「ニュースステーション」(テレビ朝日)の久米宏さん、「スーパータイム」(フジテレビ)の黒岩佑治さん、「マネー情報」(テレビ東京)の小池百合子さん・・・。この人たちとはほぼ同時期に報道番組のキャスターと作家という関係で仕事をしていました。その後の皆さんのご活躍はご存知の通りです。
その一方で、私自身は個人的にスポーツには詳しかったので、スポーツ番組の企画や構成の仕事の依頼が数多くきました。当時、小型VTRの開発が進みスポーツ番組が急増していく中で、世界のスポーツ事情に通じている放送作家が求められていたのだと思います。スポーツ番組は本当にいろいろなものを担当しましたが、大きなものとしては1991年「東京世界陸上」、1992年「バルセロナオリンピック」、1996年「アトランタオリンピック」(日本テレビ)を担当したのは、強く印象に残っています。そして1990年にWOWOWが開局するのでボクシングの特別番組を担当してほしいという依頼が入ってきたのです。12月にマイク・タイソンの復帰戦を生中継するので、その事前番組の「マイク・タイソンの軌跡」という番組を制作することになりました。この時はスポーツライターの故・山際淳司さんに司会をお願いしたのですが、何もかも番組作りという点では経験不足で、番組を組み立てて構成する作家としては結構大変でした。しかしそれでも、それがベースになって翌年から「エキサイトマッチ」の本放送が開始されました。今から振り返るとそのときはかなりバタバタした状況でしたが、それ以来この「エキサイトマッチ」は現在に至るまで35年も続いてきたのですから、日本のボクシング界にとっては欠くことのできない伝説的な番組になりましたね。「エキサイトマッチ」については、また機会を改めて、当時のことをお伝えしたいと思っています。
大学教授の仕事と研究について
今村 : 放送作家の仕事は、朝昼晩24時間体制で寝る暇もないほど過酷なものです。若いときは無理も効きますが、いつまでも続けていけるほど甘い世界ではありません。私自身は40代になったら、国際法や国際政治をベースにしてメディアやジャーナリズムの研究を中心に大学で研究者になりたいと考えていました。1997年から大学で教鞭をとるようになり、メディア論やジャーナリズム論や放送論など担当しました。早稲田大学理工学部、昭和女子大学一般教養科、日本大学法学部、等で講師を務めました。2001年に埼玉県飯能市にある駿河台大学文化情報学部(現メディア情報学部)に教授として赴任することになり、放送作家の仕事と両立させるのは難しくなったので、大学の仕事に専念することになりました。その後、駿河台大学には20年間所属し4年前に退職して名誉教授に就任しました。その間、大学院現代情報文化研究科科長、大学院総合政策研究科科長、文化情報学研究所所長、等々の役職を長く担当しました。大学の仕事というのは、研究だけでなく入試業務や学生の世話などもあって現代の大学教授はかなり大変です。また役職者になると学内の重要事項を決定する会議に出席したり、また大学を代表して関係各所に挨拶に行ったりする必要もあるので、授業や研究以外にも時間に追われることになります。私は学部も大学院も講義をもっていたので、毎週、その準備もありましたし、学部や大学院のゼミの指導もしなければなりませんでした。加えて長らく学部の人事委員長にも就いていたので、教員の採用や昇任等の人事業務も絶え間なくありました。いずれも責任の重い仕事ばかりでしたが、それなりに20年間、充実した時間を過ごすことができたと思っています。
それからゼミ論、卒論、修士論文等の学生の論文指導というのがあるのですが、学部や大学院の私のゼミでは、主にメディアやインターネット等に関する研究テーマを設定して論文を執筆させて、最終的には論文審査と口頭試問を経て学位授与という手続きを取ります。特に論文を完成させるまでのプロセスが大切なのですが、大学に提出する論文である以上、しっかりとした学問的な研究方法に基づいた調査・分析をさせ、正しい日本語で論文執筆するように指導しました。近年の学生はパソコンやスマホばかり使用しているせいか、手書きの文章を書くことが苦手な学生が多く、基本的な漢字が書けなかったり中学で習うような日本語の文法を知らなかったりすることがありました。また駿河台大学には主にアジア各国から数多くの留学生が来るのですが、彼らの多くが日本のマンガやアニメのことしか興味がなく、研究の基本的な考え方から教える必要もありました。そういうとき、私はよくオリンピックやサッカーなどのスポーツの話を例にして、日本人学生と留学生の意思疎通をさせたりしたのですが、中にはボクシングオタクのような留学生もいて、過去の日本人ボクサーと自国のボクサーの話をしてあげると大喜びしていました。メディアや情報を勉強するにしても、やはりスポーツには国境がないと感じました。そういう点から言っても、ボクシングとメディアの関係を本格的に研究対象とすれば面白いのではないかと思います。ボクシングは1世紀以上の歴史があるわけですが、ただボクサーの勝ち負けだけでなく、もっと総合的な視点から学問研究の対象とすれば様々なことが分かったり、新たな問題提起に繋がったりするのではないかと思います。こうしたことも「ボクシング情報ラボ」を始めた理由のひとつです。
ボクシング情報ラボの活動と今後について
今村 : ボクシング情報ラボが開設されましたが、実はこれは3年ほど前から計画していたことです。4年前に私が駿河台大学を退職して名誉教授になりましたが、少し時間が取れるようになったので浜田さんと前田さんとも話をして、ボクシングをもっと幅広い立場から研究するシンクタンクのような組織が出来ないものかと相談したのがきっかけでした。ただし当初から予算もないし人材もいない中で、どのように運営していけばよいのか、なかなか妙案がありませんでした。
昨年、浜田さんが世界チャンピオン会の会長に就いたのを契機としてホームページを立ち上げることになり、それと連動させる形で「ボクシング情報ラボ」のブログを始めることになりました。とりあえず活動計画を示して少しずつ活動の幅を広げていきたいと思っています。ここで私とお二人との関係を簡単に説明しておきましょう。
浜田剛史さんと最初に会ったのは、1990年12月にWOWOWでマイク・タイソンの特番を制作することになり、そのときの解説者と担当の構成作家という形で会いました。当時はまだWOWOWは辰巳のスタジオが出来る前で、浅草のROXスタジオというところで収録が行われました。そこで初めて浜田剛史さんと会いました。浜田さんには特別な思いがありました。浜田さんがレネ・アルレドンドを1RにKOして世界タイトルを獲ったのが1986年7月24日でしたが、実はその日は私の誕生日でした。当日はテレビでその様子を見ていましたが、この人とは何かご縁があるかもしれないと感じていたのです。そして何よりも圧巻だったのは、浜田さんが衝撃的なKO勝をして場内が大騒ぎになっているのに本人は至って冷静で、試合後のインタビューでも何事もなかったかのように一言一言、答えていたことでした。長い年月をかけた末に念願叶って世界チャンピオンになった直後は、間違いなく人生最高の時でしょうから、誰でも取り乱したり大騒ぎしたり言葉にならなかったりするのが普通だと思うのですが、この人はどうしてこんなに冷静でいられるのだろうと思ったりしました。私自身もそういうところがあるので、もしかするとどこかでご縁があるかもしれないと直感したのかもしれません。
それから4年後、浅草のROXスタジオで初めて浜田さん会ったときも、なぜか初対面とは思えないような気がしたものです。それ以来、私はWOWOWエキサイトマッチを10年間、担当しましたが、ほぼ毎週のように番組の打ち合わせや収録や、次のビッグマッチの仕込みなど話をする機会がありました。エキサイトマッチでは世界中から最高峰の世界タイトルマッチの試合が届いてきました。それまでの視聴者は日本人ボクサーがいかにして世界タイトルを獲るのかということばかり関心が集まっていたと思いますが、このエキサイトマッチでは外国人同士のスーパーファイトを紹介することにより、世界の最高峰はこれだけスケールが大きな世界であることを伝える目的もありました。解説の浜田剛史さんとジョー小泉さんは、このような目的を実現するには最適のコンビでしたが、いかんせんこれではボクシングマニアだけを対象とした番組になってしまいます。WOWOWのスタッフも番組制作の経験が少ない人が多かったので放送開始当初は試行錯誤の連続でもありましたが、浜田さんとジョー小泉さんといつも話していたことは、ボクシングの本物志向を貫いていくという点ではぶれないようにしようという点では一致していました。WOWOWは日本では初めての有料チャンネルでもありました。毎回世界の最高峰のボクシングの試合を見ることができるわけですから、この番組にはお金を出しても見る価値があるという意識を持ち続けたいと考えていました。結果的にはその基本方針が良かったのでしょう。安易にバラエティ色に染まったりせずに、しっかりとした番組作りを続けてきたことが視聴者にも受け入れられたのだと思います。
その後、私は駿河台大学教授に赴任しましたが、それでも時折、浜田さんとは電話で試合のことや番組へのアドバイスやボクシング界のことなど、いろいろと意見交換してきました。浜田さんは、今や日本のボクシング界を代表する存在ですが、同じ番組を担当した作家として、またメディアやジャーナリズムを専門としてきた研究者として、何か一緒に協力して出来ることはないかと考えていたのです。そういう経緯があって、ボクシング情報ラボのブログを開設することになったわけです。
またボクシングビート元編集長の前田衷さんとも、長いお付き合いです。私がエキサイトマッチを担当するようになってから間もなくして、当時、前田さんが編集長をされていた「ワールドボクシング」に「グローブ雑学」というコラムを連載させていただくことになりました。また「ワールドボクシング」の特集号では長編の原稿を担当したり、年末のボクシングの有識者による最優秀ボクサーベスト10を選ぶ選者に加えていただいたりしました。前田さんが書いていた原稿は「ボクシングマガジン」の時代から毎月のように読んでいましたが、本当にボクシングの生き字引のように思っていました。ジョー小泉さんと前田衷さんは、日本ボクシング界の偉大なるご意見番だと思いますよ。今回、前田さんにはボクシング情報ラボの趣旨にも賛同いただき事務局長を担当していただくことになりました。ボクシングは各々の時代の移り変わりが速いものですが、それを歴史的な視座から捉えられる希少な人材です。ボクシングに限らず専門誌などの活字メディアが次々と姿を消していく中で、過去の貴重な情報を次世代にも伝えていかなければなりません。これからのネットの時代にも十分活かすことが出来るようなボクシングの情報管理やアーカイブの機能などを、ともに考えていただきたいと思っています。
このボクシング情報ラボは、決して規模を大きくしたり利潤を求めたりするようなことが目的ではありませんが、できる限り少数精鋭でボクシングの情報を広く深く掘り下げて考察していけるような環境を作っていきたいと思っています。またこの会の趣旨に賛同してくださる方を対象とした企画も今後講じていく予定です。こうした活動が若い世代にも広がり、ボクサーやトレーナーだけでなく、記者、ライター、カメラマン、エディター、放送作家、ディレクター、等、ボクシング情報に関係するプロを目指す人たちの人材育成に繋がっていくことを期待しています。

理事長:今村庸一
1956年生まれ。駿河台大学メディア情報学部名誉教授。メディア論。東京大学大学院社会学研究科卒。
放送作家として数多くのスポーツ番組の企画・構成を担当。1990年よりWOWOWエキサイトマッチの構成を10年間担当。「ワールドボクシング」にもコラムを連載するなど多数執筆。